テレホン法話
~3分間心のティータイム~
【第805話】「ノートを取る」 2010(平成22)年5月1日-10日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第805話です。
「とる」という言葉には様々な意味があります。漢字も手元の辞書によると、27種類もあります。「手に取る」から「天下を取る」まで、実に広範囲です。調べて記録するという意味で、「ノートを取る」という言い方もあります。そのノートの取り方で興味深い話をお檀家さんの70代半ばの男性から聞きました。
その方の小学生時代のこと。当時まっ白い紙のノートなど誰も持っていなくて、新聞紙を切って綴じたものをノート代わりに使っていました。黒い鉛筆で書いたのでは字が見えないので、赤い鉛筆で書いたそうです。6年生の時たまたま、地元出身でハワイに渡って成功した人が里帰りをした折に、6年生全員にノートをプレゼントして下さいました。生まれて初めて手にするまっ白いページのノートです。誰もが有り難くて、もったいなくて、とてもそのノートに字を書く気にはなれなかったそうです。
今から60年以上も前の、戦前の話ですが、似たような話は今もカンボジアにはあります。今から18年前に私がカンボジアに行った時、粗末な校舎で授業を受けていた子どもたちには、ノートも鉛筆もなく、板状の石の「石盤」にチョークで文字を書いていました。一杯になったら、消してまた書く。当然記録には残りません。「ノートを取る」という表現は当たらないのです。
それから何度かカンボジアを訪れ、学校の子どもたちにノートや鉛筆をプレゼントする機会がありました。みんなうれしそうに喜んでくれました。そのご縁が続いて現在は、カンボジアの子どもたちに絵本を贈るお手伝いをしています。この間、ハック・ソイ・トライ君という15歳の少年から写真入りの礼状が届きました。15歳ですが小学校5年生で、8人家族。本を読むのが大好きで、週に1回図書館に通っているそうです。将来は運転手になりたいという夢まで書いてありました。
白い紙に鉛筆で書かれた現地の言葉は読めませんが、日本語訳が添えられたその手紙には、遠く離れても心を伝えられる、白い紙と文字の有り難さが滲み出ていました。ノートを取ることによって、字を覚え言葉を覚えられるようになります。ノートを取るとは、自分の未来を描くことにも繋がるわけです。5月は「子どもの日」があります。世界の困っている子どもたちの明日ために、私たちができることを進んで行いたいものです。決して、よその国のことは関係ないなどと、ノーと言わないようにしましょう。
それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。
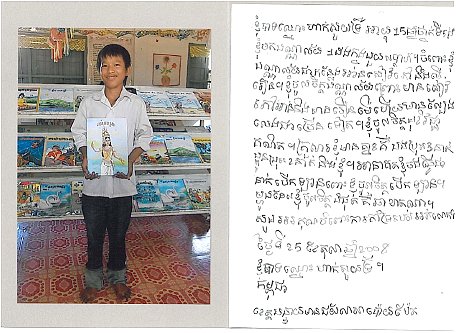
最近の法話
【1317話】
「18歳と81歳」
2024(令和6)年7月21日~31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1317話です。 「年齢7掛け説」というのがあるそうです。健康な現代人の年齢は、3割若く数えても大丈夫だということです。60歳なら42歳、70歳なら49歳、80歳なら56歳という風にです。50代・60代の頃はさもありなんと思っていましたが、さすがに70歳を超えると、8掛け・9掛けが現実に即している気がします。 さて、ある方から「... [続きを読む]
【1316話】
「不二山」
2024(令和6)年7月11日~20日

住職が語る法話を聴くことができます お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1316話です。 東京都国立市では、駅前から伸びる通りを富士見通りと称しています。晴れた日には富士山を望めるからです。2年前にこの通りにマンション建設の話が持ち上がりました。地元では景観をめぐって反発したものの、建築基準法上の問題はないということで着工、先月完成しました。しかし引き渡しまじかにな... [続きを読む]
【1315話】
「一心松」
2024(令和6)年7月1日~10日

住職が語る法話を聴くことができます 元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1315話です。 東日本大震災で大津波を目撃した人は、「松林の上から黒い煙が出ているように見えた」と言っていました。最大波12.2㍍ともいわれる津波が、わが山元町の沿岸部の松林を根こそぎ破壊しました。松は養分や水分がなくても育ち、塩害や風にも強いことから、防風林・防砂林として用いられてきました。し... [続きを読む]
テレホン法話
~3分間心のティータイム~
- 2024年
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2023年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2022年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2021年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2020年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2019年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2018年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2017年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2016年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2015年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2014年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2013年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2012年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2011年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2010年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2009年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
- 2008年
- 12月
- 11月
- 10月
- 9月
