テレホン法話 一覧
【第938話】 「2分20秒」 2014(平成26)年1月11日-20日
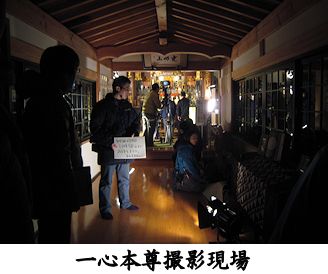
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第938話です。
年末年始にかけて、テレビ三昧だった人でも、画面を見ているだけで、それを映すカメラまで見ることはできません。カメラマンの姿もわかりません。その他、照明や音響に携わる方、台本を書く方、番組すべてを統括する監督など、画面には現れませんが、実に多くの方の働きによって、一つの番組が放送されています。
大晦日恒例のNHKテレビ「ゆく年くる年」の中で、徳本寺からの中継も放送されました。除夜の鐘が響く中、ライトアップされた本堂が映し出されました。そして一心本尊さまにお参りする人々の姿がありました。一心本尊とは、徳本寺の末寺である徳泉寺の本尊さまです。徳泉寺は東日本大震災の津波で本堂等がすべて流されましたが、本尊さまだけが奇跡的に発見されました。どんな災難に遭っても、人々の支えになろうとする一心で踏み止まったものと信じて、「一心本尊」と名付けられ、徳本寺に仮安置されています。
一心本尊の徳泉寺を復興するために、現在「はがき一文字写経」を展開していますが、全国から寄せられた何百枚ものはがきも画面いっぱいに映し出されました。そしてこの山元町の名産であるイチゴが一心本尊さまに供えられていた映像も印象的でした。イチゴの見事な赤い色は、復興のシンボルと映ったのではないでしょうか。
番組は、全国13ヵ所の年越しと年明けの風景をリレーで紹介する30分間の生放送です。1ヵ所の放送時間はわずかです。しかし、そのわずかな時間のための準備は、半端ではありませんでした。最初に徳本寺からの中継の打診があったのは、2ヶ月ほど前でしょうか。それから10回近く打ち合わせを重ねました。本格的な現場の設営に入ったのは3日前からです。
本堂・境内をライトアップするために、照明用の高い櫓が組まれました。不測の事態に備えて、予備の中継アンテナも小高いところに設置されました。中継車や機材を積んだトラックは、ずっと止めっぱなしですので、夜間は警備員がついています。物々しいと思えるほどの準備態勢です。本番の画面は主に3ヵ所を映すのですが、カメラは1ヵ所に2台も3台も設置されます。総勢5〜60人ものスタッフが準備段階からチームを組んで動いていました。カメラ・照明のテストをはじめ、入念なリハーサルが繰り返されます。全国をリレーする放送ですので、1秒のミスも許されないのです。こうして映し出された徳本寺からの中継は、2分20秒。今回の各地の中継の中では、放送時間は長い方だったそうです。
いくらテレビ三昧になっても、見ることができるのは、画面という限られたものだけです。その画面の1分1秒にかける裏方の働きは計り知れないものがあります。それを思うと、私たちの今日という人生の画面を映し出すまでに、どれほどの裏方のおかげがあったのでしょう。1分1秒を疎かにせずに、この一年を過ごしましょう。
ここでご報告致します。12月のカンボジア・エコー募金は、128回×3円で384円でした。ありがとうございました。
それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。
【第937話】 「ずぼら」 2014(平成26)年1月1日-10日
 お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第937話です。
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第937話です。
あけましておめでとうございます。
どなたさまも、新たな気持ちでお正月を迎えられたことでしょう。今年こそはと思うことの一つに、どうしても東日本大震災からの復興を挙げなければなりません。今年の3月で丸3年を過ごすことになります。「石の上にも3年」の言葉通りに、何らかの報われた結果が出なければ、被災地ではいつまでもずるずると、耐え忍ぶ生活を強いられることになります。被災地以外では、3年という区切りのいい数字につられて、「震災のことはもういいだろう」という雰囲気にならないか、心配です。
復興が目に見えて進まない原因は、被災地・被災者それぞれによって、様々なことが考えられるでしょう。個々の対応については、ひとまず置くとして、リーダーが心意気を示さなければ、復興が上げ潮に乗ることはありません。この3年間、その時々の日本のリーダーは、復興に関しては、ややずぼらな印象を受けました。決めなくてもいいような特別秘密保護法を即決した勢いから比べたら、尚のことです。その勢いを復興関連のことに向けて欲しいものです。
ところで、「ずぼら」とは、ご存じのように「するべきことをちゃんとしないこと」を言います。その語源は、「坊主(ぼうず)」をひっくり返した「主坊(ずぼう)」にあるというから驚きです。昔、修行を忘れて遊んでばかりいた坊さんたちを、軽蔑を込めて「ずぼう等」と呼んだそうです。やがて「ずぼら」になって、坊さん以外の人でも、いい加減な人を「ずぼらな奴」などというようになりました。
私は徳本寺・徳泉寺の住職を勤めています。ある意味、2ヵ寺のリーダーです。どちらの寺も甚大な被害があり、復興に取り組まなくてはならない状況です。これまでも、それなりに尽力してきたつもりですが、まだまだ思ったような結果を出すまでには至っていません。決して、ずぼらを決め込んでいたわけではないのですが、あまりに厳しい現実があります。
徳本寺は津波で壊滅状態になった中浜墓地の移転、徳泉寺は流された本堂等の伽藍の復興。どちらも檀家さんも被災しているので、その協力を得ることは困難です。それでも、3年も経って復興の兆しが見えなければ、ほんとうに「ずぼらな和尚だ」と言われかねません。今年こそはリーダーとして心意気を示し、先ず、中浜墓地は春頃までに移転造成を完成させます。徳泉寺は境内が災害危険区域になっているため、境内地の移転も視野に入れつつ、伽藍復興を進めます。今年の干支の馬にあやかり、復興へ馬力アップです。みなさまも被災地へのバックアップをよろしくお願い申し上げます。ずぼらな復興で終わらないためにも・・・。
それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。
【第936話】 「除夜の鐘」 2013(平成25)年12月21日-31日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第936話です。
「9」という数字を、日本人は好まないかもしれません。「苦しみ」の「苦」を連想するからでしょう。しかし、1から9までの整数の最後の数であり、「久しい」の「久」に通じます。また、数が多いことやきわめる、完成する数とも言われます。中国では昔から「9」は最高の尊い数「聖数」として崇めました。古代中国では、皇帝を九天、皇居を九重と呼びました。
その9の倍数に108があります。ご存じのように、大晦日の除夜の鐘は、108回撞きます。私たちが持つ108の煩悩を悔い改めて、新たな心で新年を迎えるためと言われています。人間が生きていく上で、色々な悩みや煩いが伴うものです。それを一つ一つ分析していくと、108になるという解釈もあります。実際はそのような数で限られるものではないでしょう。煩悩無量と言ってもいいほどです。9の12倍である108は数えきれないほど多くのという捉え方が自然かもしれません。
さて、除夜とは文字通り「夜を除く」ことですが、夜とは「心の闇」であり、それを一つ一つ取り除くことでもあるでしょう。闇は苦しみの象徴です。それらのほとんどは、自分の心の物差しで判断して現れた結果です。その物差しとは、自分中心の「俺が」という尺度です。その尺度に合わないものが苦しみの原因となります。思い通りにならなかった苦しみより、何かのおかげでよかったことを数えることも、除夜につながるはずです。
毎日の天候だって、自分の都合で一喜一憂しています。「借りた傘も、雨があがれば邪魔になる」といいます。傘を借りたとき思った「おかげさま」という気持ちは、心に沁みこまないうちに、乾いてしまうかのようです。今年の除夜の鐘は、忘れかけた「おかげさま」の一つ一つを思い起こしながら耳を澄ますのもいいでしょう。東日本大震災から3度目の除夜であり、新年を迎えます。どれだけの「おかげさま」があってここまでこられたかに、想いを馳せることも大事です。来るべき年は、そのおかげさまに報いられるように復興が進むことを願いましょう。
「鐘は一里鳴って 二里響き 三里わたる その響いてわたる間に祈るのである」と言ったのは、永六輔さんです。梵鐘のいいところは、単に音が鳴るというのではなく、響き渡るという点です。どこまでも祈りが届くような気がします。除夜の鐘を撞きながら、或いは聴きながら、復興の一日も早からんことを祈りましょう。震災という苦(9)しみを超えて、復興への及(9)第点を達することができますようにと・・・。
ここでお知らせ致します。今年の大晦日のNHKテレビ「ゆく年くる年」の中で、徳本寺の除夜の鐘も中継される予定です。除夜の鐘を撞きに是非ご来山下さい。遠くの方はテレビでお聴き下さい。
それでは又、来年1月1日よりお耳にかかりましょう。
【第935話】 「被災地の星」 2013(平成25)年12月11日-20日
 お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第935話です。
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第935話です。
「世紀の大彗星」と騒がれ、冬の夜空を飾ると期待されたアイソン彗星は、11月29日未明に太陽に最も近づいた際に散ってしまいました。彗星は長い尾を作るのでほうき星ともいわれます。アイソン彗星もその尾っぽが長く、本体の「核」もそこそこに大きい「大物」との見方がありました。しかし、専門家の予想より核が小さくて、太陽の熱や重力に耐えられず、急激に蒸発し崩壊したというのです。まるで「彗星のように現れて、彗星のように消えて行った」と自作自演でもしたかのようです。
私たちが住むこの地球も星の一つです。いつか崩壊して消えてしまうことはないのでしょうか。あの東日本大震災の惨状を目の当たりにしたとき、地球上でこんなことが起こるのかと目を疑い、今自分が立っている場所がどこなのか、どんな時代に生きているのかと、頭の中が混乱していたことを思い出します。少なくとも今まで馴染んでいた地球ではない、ある種の地球の崩壊を感じました。その崩壊を強く感じたものの中にイチゴ畑があります。
地域ブランド「仙台いちご」の産地として知られる我が山元町と隣町の亘理町は、東北最大のイチゴ畑が広がっていました。温暖な気候と沿岸部の砂地がイチゴ栽培に適していたのです。それが大震災の大津波で95%の面積が被災しました。ビニールハウスのビニールは跡形もなくなり、鉄パイプは針金を曲げたかのように無残に絡み合っていました。しかし、ボランティアの支援もあり、いち早く畑に散乱した瓦礫を取り除き、復興へ取り組みました。そこに重大な問題が起こりました。津波による塩害です。砂地や地下水に塩分が入り、イチゴ栽培は絶望的な状況に追い込まれました。
そのとき、町から提案されたのは「高設栽培」による「いちご団地」構想です。これまでそれぞれの畑で作っていたイチゴを、できるだけハウスを集約して、まとまって栽培しようというものです。しかも土を使いません。イチゴは地面から1mぐらいの高さのヤシガラの入ったプランターに植えられます。プランターの上には管が張り巡らされ、肥料の入った養液が苗に与えられます。室温や水の管理、収穫の際の体の負担も従来よりずっと楽になるといいます。
こうして、震災から2年8カ月後の11月7日に真っ赤なイチゴの初収穫がありました。「明日 地球が滅びようとも 君は 今日 りんごの木を植える」という言葉があります。崩壊寸前の被災地に、諦めないでりんごならぬいちごの苗を植えた人々。しかも彼らいちご団地の生産者の7割が住居を失い、今も仮設住宅から栽培に通っています。住まいの崩壊にも負けずに、イチゴを実らせた情熱は、復興の象徴でもあります。いまイチゴの輝くような赤い実は、被災地の星です。
ここでご報告致します。11月のカンボジア・エコー募金は、115回×3円で345円でした。ありがとうございました。
それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。
【第934話】 「臘月」 2013(平成25)年12月1日-10日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第934話です。
12月の別名に「臘月(ろうげつ)」というのがあります。「臘」にはその年に生じた百物をまつって年を送る祭りの意があり、年の暮れも意味します。禅寺では12月1日から8日までは、坐禅三昧の修行期間にあたり、これを12月の8日間ということで、臘八接心(ろうはつせっしん)と言います。
お釈迦さまは、29歳で出家なされ、山に籠って6年もの間、難行苦行を続けられます。しかし、それではお悟りを得られないことがわかり、山を下ります。尼連禅河(にれんぜんが)で沐浴され、スジャータという娘に乳粥の供養を受けて、体力を回復された後、菩提樹の下で坐禅三昧に入られました。8日目の朝、即ち12月8日の明け方、東の空に瞬く明けの明星をご覧になり、お悟りを開かれました。その因縁が臘八接心となっているのです。
そのお悟りというのは、すべての現象はさまざまな原因や条件によって成り立っている「縁起の法」のことです。原因があっての結果であるから、その因果関係を悟れば苦悩から解き放たれるということに気づかれたのです。しかし、この境地を一般の人が簡単に理解できるわけはありません。お釈迦さまは、自分だけが悟りを得た悦びに浸ることなく、一人でも多くの人が、早く迷いから抜け出し、幸せになることを願って、伝道の旅に出ました。こうして80歳で亡くなるまでの45年間、各地で説法を続けられたのです。
私たちは一人で生きていくことはできません。多くの人や物に支えられて生きています。その私も誰かの支えになっているかもしれません。世の中のすべてはお互い支え合っているとことに思いが至れば、お釈迦さまのお悟りに近づけるのではないでしょうか。宮沢賢治の「全世界の人が幸福にならなければ、個人の幸福はあり得ない」という想いは、お釈迦さまの心そのものです。
さて、今年の臘八接心の中日12月4日は、東日本大震災発生から数えて、ちょうど千日目になります。千年に一度といわれる災害を経て、千日を生きてきました。千年という歳月からすれば、365分の1です。しかし、苦しみを抱えた人々にとっては、明日が見えず気が遠くなりそうな時間でした。日本全体からすれば、わずか365分の1という歳月で、千年に一度の記憶が遠くに行ってしまうのではないかという不安があります。臘八接心中に震災千日目を迎えたという因縁を想い、自分だけの悟り・幸福を願うのではなく、苦しみにあるすべての人の幸福をも祈りたいものです。
被災地ではこの千日間、百物ならぬ物心両面の数えきれない支援をいただきました。被災地の人はその支援を心にまつって臘月を送ります。みなさまには、千年には千回の臘月があることを想い、いつも臘月の心を忘れないで下さい。スジャータの乳粥がお釈迦さまのお悟りへの支えとなったように、みなさまの支えにより、わたしたちも、いつの日か輝く星を仰ぐことができるよう精進します。
それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。
【第933話】 「津波の碑」 2013(平成25)年11月21日-30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第933話です。
「かけた情けは水に流せ、うけた恩は石に刻め」と言われるように、石に記しておけば、末代に亘って伝え続けられるということでしょう。墓石や様々な記念碑はその性格を十分に表しています。7年前の平成18年5月発行の山元町ふるさと学習会の随筆集に、当時会長だったSさんは、「津波の碑」について一文を寄せています。
「中浜町の東方塩釜場と松林の間に、バッケと呼ばれる高さ3メートル位の砂丘の感じの丘が南北に伸びている。このバッケの中程に津波の碑がありました。やがてその地は荒れて、津波の碑は竹藪に覆われて見えなくなったので、数年前に海岸通りの町道に移設された。碑には『地震があったら津波の用心』と大きく刻まれてあり、裏面には、明治二十九年と昭和八年の津波の被害状況が記されている。この碑は、昭和八年三陸津波に対する義援金の一部で建てられたとある」
この山元町にもその昔、津波の被害があったということを改めて知りました。記録によれば、昭和8年の三陸地震津波は、3月3日午前2時31分に起こった地震で、震源地は金華山沖280キロメートル、約30分後に三陸海岸に津波が襲来。県下の海岸地帯で、死者3百数十名を数え、家屋の倒壊、流出が相当数ありました。山元町では、津波の高さは2メートル以上に達し、重軽傷者18名、家屋の倒壊、漁船、漁具の流出、損壊もあり、床上・床下浸水家屋も続出とあります。
この津波の碑は高さ3メートルもあるものでしたが、この度の大津波で流されて、現在は震災遺構として残っている中浜小学校の校庭に横倒しのまま置かれています。いずれ然るべきところに設置されるのでしょうが、記念碑の役目とは、どういうことなのかを考えさせられます。津波の碑が建てられてからまだ80年しかたっていません。しかし、石碑の存在を知る人は少なく、何が書いてあるのか、ほとんどの人が分かっていなかったような気がします。墓石のように年に何回かお参りするということもないでしょうから、尚のことです。
石に刻んでそれを建てた、それだけで十分ではないのです。その石を通して日頃から、刻んである内容について、伝え続けていくということが大事でしょう。「地震があったら津波の用心」という石碑を調べて、文章にもして私たちに伝えてくれた肝心のSさんですら、逃げ遅れてこの度の大津波の犠牲になってしまいました。そして記念碑の建っていた中浜地区は町内でも最も多くの犠牲者が出たところです。
石だって不変でないことは十分に証明されました。亡きSさんから私も町の歴史を教えていただき、恩を受けました。そんな恩も含めて、この度の大震災について、一人ひとりの心の記念碑にこそ刻んで、伝え続けていくことにより、非の打ちどころがない「津波の碑」と言えるのではないでしょうか。
それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。
【第932話】 「お墨付き」 2013(平成25)年11月11日-20日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第932話です。
仕事柄、毎日のように筆を使いますが、いわゆる作品は書きません。必要に迫られて書く塔婆や位牌の文字がほとんどです。そこには芸術性も味わいもありません。極めて事務的で、書道とも言い難いです。しかし、先輩の和尚さんに言われたことがあります。「和尚さんは筆が立つに越したことはないが、塔婆や位牌の字は拝まれるものだということを忘れてはならない。上手下手よりも、拝んで有り難いと思われるような字を書きなさい」と。
上手下手の区別はある程度つくこともありますが、拝んで有り難い字というのは、書いている私も解りません。書の世界はほんとうに奥が深いものです。ましてや、展覧会に出品するような作品ともなれば、どれもが素晴らしいものです。そこで入選作を選ぶのは至難なことでしょう。どの作品もまさに紙一重の差もないくらいでしょう。だからというわけではないでしょうが、106年の歴史を誇る日展の「書」で、有力会派に入選数を事前に割り振るという不正が発覚しました。
書や絵などの芸術性は、数値化できるものではありません。それだけに審査の難しさと、審査基準の解りにくさも生まれます。今回の不正の下となったものに「天の声」があるといいます。審査員が入選を決めても、直前に日展顧問といわれる方の無言の圧力により、審査結果を取り下げ、「天の声」の指示通りに差し替えたという事実が明るみになりました。
日本美術界では日展入選という実績が何よりものをいうそうです。更に階級制度が厳然としてあります。優れた賞を受賞するたび、階級が上がります。階級が上がるほど弟子が集まり、収入も増えるしくみになっています。日展の入選数は会派運営に多大な影響を及ぼします。入選数が少ないと弟子が集まらず、別の会派に移ることもあります。会派間の入選者の割り振りは、ある意味会派同士の共存共栄に繋がっているのかもしれません。しかし、それは芸術の命を無視して、会派の命だけを考えている姿です。当然の如く、そこにはお金が絡んできます。出品するだけでは入選はできない、審査員の作品を買わないとだめとか、入選すれば高額の謝礼を会派代表に持っていくとか、さもありなんです。
中国・北宋の時代の蘇軾(そしょく)の言葉に「人 墨を磨るに非ず 墨 人を磨る」というのがあります。日展の書道界で一目置かれているような方は、これまでにどれほど墨を磨って現在に至ったことでしょう。ご自分の地位や会派の存在だけを磨いてきたのでしょうか。書を通して人格も磨かれていれば、「お前の書には、その人格が滲み出て拝みたくなるほどだ」という、それこそ天からのお墨付きがいただけるはずなのですが・・・。
ここでご報告致します。10月のカンボジア・エコー募金は、131回×3円で393円でした。ありがとうございました。
それでは又、11月21日よりお耳にかかりましょう。
【第931話】 「ブランド」 2013(平成25)年11月1日-10日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第931話です。
あるホテルのピアノバーでのこと。男性がピアニストにリクエストをしました。「『砂漠の赤い月』を弾いてくれ」ピアニストはこともなげに、弾きはじめました。男性は連れの女性に言いました。「あのピアニストは嘘つきだ」「どうして」「だって「『砂漠の赤い月』なんて曲は、どこにもないんだ。ちょっとからかってみたのさ」「そうだとしたら、粋な嘘つきね」と言って、女性はうっとりとその音色に聴き入っていました。
『砂漠の赤い月』という曲は、ありそうなタイトルですが、立派な嘘。ピアニストは曲を知らない、弾けないとは一切言わず、それらしい雰囲気の演奏を披露して、誰をも良い気分にしたのでした。騙されても心地よい嘘もあるのですね。昔聞いた「ちょっといい話」です。
さて、昨今のホテル業界では、ちょっとどころか、「とんでもなく悪い話」があるようです。大阪市の阪急阪神ホテルズ系のレストランで、メニュー表示と異なる食材が使われた問題で、社長は辞任に追い込まれました。「ブランド全体の信頼の失墜を招いた。故意に欺く意図はなかったが、偽装と指摘されても仕方ない」などと弁明していました。
バナメイエビを「芝海老」として提供したのは、調理担当が小さなエビは芝海老と称するものという認識の誤りから派生したといいます。九条ねぎを使っていないのに、九条ねぎと称したのは、添え野菜の変更は表示の必要がないとサービス担当が判断したという訳のわからない言い訳です。
よほど舌の肥えた人でも、食材の違いを指摘できる人は多くありません。ただおいしいものは、食べたい。そうなると、どこそこの何はおいしいという、評判や知識が舌の代わりになってきます。そこは食べる方もブランドに頼ってしまうわけです。ましてや、一流のホテルで提供されたものとなれば、全幅の信頼を置いてしまいます。少々値が張っても、「やはり本物は違う」と満足して、財布の紐を緩めるわけです。
名前やブランドが広く知られるようになるには、それ相当の時間がかかります。しかも誰からも信用されるような態度や物を提供し続けて、はじめてみなさんに認知されるようになるのです。それだけに、たった一つの裏切りであっても、それまで信用してきたことへの反動が激しくなることは想像に難くありません。
私たちには、仏教徒として守らなければならない十の戒めの第4番目に「不妄語戒(ふもうごかい)」があります。嘘や偽りを言ってはならないということです。これは、嘘や偽りを言おうとしても、仏の教えを信じるものとして、とても言えるものではありませんとも解釈できます。ホテルにおいては、偽りをしようとしても、ブランドが邪魔をしてとてもそんなことはできませんという気概が求められます。「砂漠の赤い月」を見上げるように、乾いた現代にあって、聳えるホテルの建物を嘘の塊とみられたらおしまいです。そうなればブランドもブラインドも閉じなければなりません。
それでは又、11月11日よりお耳にかかりましょう。
【第930話】 「復興笑」 2013(平成25)年10月21日-31日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第930話です。
アンパンマンの作者やなせたかしさんが、10月13日94歳で亡くなりました。やなせさんは童謡の「手のひらを太陽に」の作詞家としても知られています。「ぼくらはみんな生きている 生きているから笑うんだ」という有名な一節があります。
私たちは一人で生まれて一人で死んでいく定めです。しかし、生まれてから死ぬまでの間、つまり生きている間は、決して一人ではありません。様々な人に支えられたり、いろいろなもののおかげで生かされていることを実感します。この私も誰かの支えになることもあるかもしれません。やなせさんは「ぼくらはみんな生きている」と歌っています。「ぼく」ではなく、「ぼくら」というところが肝心です。そうでないと次の一節「生きているから笑うんだ」につながり難くなります。屁理屈のようですが、「ぼく」一人で笑っては気持ち悪いでしょう。一人ニヤニヤしている人を見てどう感じますか。やはり笑うときは「ぼくら」で笑い合うことが自然です。
私たちは一人でしかも泣きながら生まれてきます。そのためとはいいませんが、一人で泣いても様にはなります。しかし一人きりで笑うことができたとして、後から虚しさが募るものです。何か面白いものを見て笑うとしても、相手がいてのことです。「ぼくら」としてこの世に生きている限り、「ぼくら」で笑い合えるのが理想です。
大震災から2年7ヶ月が過ぎ、復興という言葉や現実のイメージが、人によって異なった受けとめ方をされています。すべてを失いながらも、新天地を求めて、新しい生活を始めた人もいます。大方はまだ仮設住宅に住まいしています。中には将来に対して展望が開けていない人もいます。どう考えても、これからの復興は一人二人の力で成し得るレベルではありません。一人で泣いている自分にサヨナラをする頃です。多くの人に支えられている自分をイメージしてみましょう。
一人で笑うことができないように、一人だけで復興は叶いません。多くの人の思いやりと力で復興が進んだとき、人は笑顔になります。笑顔は笑顔を呼びます。中島みゆきさんも「with」という歌の中で「ひとりきり泣けても ひとりきり笑うことはできない」と歌っています。復興はまだまだです。どなたも大震災を忘れることなく、みんなで被災地というステージに立ち、太陽というスポットライトを浴びて、「復興笑」という笑顔を演じていきましょう。
ここでご報告致します。9月のカンボジア・エコー募金は、115回×3円で345円でした。ありがとうございました。
それでは又、11月1日よりお耳にかかりましょう。
【第929話】 「やさしき覚悟」 2013(平成25)年10月11日-20日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第929話です。
江戸時代のこと、ある禅僧が弟子たちに問題を出しました。「おまえの父と母が川で溺れかけている。父と母どちらを先に助けるか、おのおの考えを述べよ」。弟子たちは議論を始めました。しかし、一向にまとまらず、答が出ません。とうとうその禅僧は、全員を叱ります。「いつまでも議論ばかりをしていたら、両親とも溺れてしまうぞ!」
命に係わる一大事というときに、悠長に議論などしていられないはずです。禅僧は弟子たちの「覚悟」を聞きたかったのです。しかし、弟子たちは出された問題は、あくまでも机上の空論だと思っていたので、黙ってしまうだけでした。「情けない、それでもおまえたちは、禅をかじった人間か!」と更に叱咤の声が飛びます。一人の弟子が恐る恐る尋ねます。「先生であれば、どうなさいますか、教えて下さい」「わしなら、手当たり次第に助けるだけじゃ」
一大事のとき、どんな行動をとるべきか、あらかじめ議論を重ね想定しておくことは大事です。しかし、現実に危機に遭遇したとき、想定のように行動できるとも限りません。最後はその人自身が腹をくくることができるかどうかです。そのためには、普段からの議論よりも、覚悟を決められる心の鍛練が大事になってきます。
さて10月1日、JR横浜線の踏切で、線路内にいた74歳の男性を助けようとした40歳の女性が、列車にはねられ死亡しました。男性は重傷を負ったものの、命に別状はありませんでした。状況はこうです。男性が線路上に横たわったまま、踏切の遮断機が降りてしまいました。先頭で踏切待ちをしていた車の助手席にいた女性は、とっさに「助けなきゃ」と言って、車を降りました。運転席にいた父親が「ダメだよ」と制するのを、振り切って行ったとのこと。踏切に入り、線路上に腹ばいになっていた男性のもとにしゃがみ込んで、動かそうとしたといいます。
目の前で犠牲になった娘のことを父親は、「困っている人を放っておけない子だった。男性には長生きしてほしい」と涙ながらに語っていました。女性を知る人たちも、道に迷った高齢者や酒に酔った人を介抱し、名前や住所を聞いて家族に連絡してあげることもあったなどと、その温厚でやさしい人柄に触れていました。
踏切事故は現実に起こり得るし、その場に立ち会うこともないとは言えません。そのことについて、議論はいくらでもできるでしょう。我がこととして現実になった時に、その覚悟ができるでしょうか。いささか坐禅をしている私ではありますが、女性のような行動をとる自信はありません。今はただ、女性のご冥福を祈りつつ、もっと手当たり次第に時間を作り、坐禅に打ち込み、「やさしき覚悟」を極められるよう精進しましょう。
ここでお知らせです。10月20日(日)午後2時、徳本寺において「第7回テレホン法話ライブ」を開催いたします。ピアノ演奏にのせて法話を語ります。特別ゲストは、津軽三味線日本一の柴田三兄妹です。入場無料。
それでは又、10月21日よりお耳にかかりましょう。
