テレホン法話 一覧
【第988話】 「太鼓判」 2015(平成27)年6月1日-10日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第988話です。
大擂鼓(だいらいく)という太鼓の打ち方があります。特別な法要で主役たる住職を迎えるときなどに鳴らす太鼓のことです。最初は小さく、段々大きな音になり、まさに雷が鳴り響くように聞こえ、クライマックスを演出します。その大擂鼓の音と思いました。5月25日午後2時28分ごろに、埼玉県北部を震源とするマグニチュード5・5の強い地震が起きたときのことです。都心では10カ月ぶりに緊急地震速報が出され、多くの人が身構えました。
私は横浜市鶴見区にある大本山總持寺におりました。紫雲臺という古い建物の部屋で、月例法話会の講師を勤めていました。建物の揺れを感じる前に、地鳴りのような音が聞こえました。あまりに近くに感じたので、地震とは思えず、何か法要があって大擂鼓が鳴っているのだろうと思ったのです。ほどなく揺れを感じたので地震と分かりました。100人を超える聴衆の方がいましたが、多少ざわつきはしたものの、立ち上がる人もなく何とか無事でした。
実はその時の法話の内容は、東日本大震災に関することでした。話は後半に入り、「ひとつの心」という歌の動画DVDを観ていただいていた時です。「ひとつの心」は大震災の津波で流された兼務寺の徳泉寺本堂復興を願って、「はがき一文字写経」を展開していますが、そのイメージソングです。歌う尼さんことやなせななさんが歌って下さっています。本堂は流されたものの、本尊さまだけは奇跡的に発見されました。どんな災難に遭っても、人々の心の支えになろうとする一心で踏み止まったものと信じて、「一心本尊」と名付けられました。
昨今は地震・津波そして火山など、いつどんな災難に遭うかわかりません。そんな時だからこそ、あの大災難に遭いながらも無事だった「一心本尊さま」を拝んで下さい。できれば災難に遭わないよう、遭っても被害が少なくて済むように願って、心した日々を過ごして下さいと、お参りの方にはお伝えしています。
本山で地震に遭ったときは、ちょうどDVDに「一心本尊さま」が映し出されていました。少なくても私は「一心本尊さま」に祈りました。どうか大きな被害が出ませんようにと。結果その通りになったのですが、図らずも「一心本尊さま」の功徳を実際に示すことができました。
それにしても「地震・雷・火事・親爺」の言い伝えは生きています。大擂鼓という太鼓で主役が登場するように、大きな地震のとき、雷のような地響きが先達となり、地震を連れてくるものだと改めて感じました。災難は忘れずにやってくると、常に身構えて祈り続ければ、難を逃れられると、「一心本尊さま」は太鼓判を捺して下さったかのようです。
それでは又、6月11日よりお耳にかかりましょう。
【第987話】 「命名」 2015(平成27)年5月21日-31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第987話です。
落語の「寿限無」は、男の子を授かった父親が和尚さんに命名を依頼します。とにかく長命であるような名前をということで、候補に挙がったものを全部付けてしまいます。「寿限無 寿限無 五劫の擦り切れ云々・・・」という名前で、実に130文字もあります。
さて、海の向こう英国では、5月2日にウィリアム王子とキャサリン妃の間に、第2子の王女が誕生しました。シャーロット・エリザベス・ダイアナと命名されました。シャーロットは「可愛らしい」とか「女の子」という意味があるそうですが、祖父にあたるチャールズ皇太子のチャールズの女性形でもあります。エリザベスは現女王ですし、ダイアナはご存じのように、ウィリアム王子の亡くなった母の名前です。「寿限無」の父親ならいざ知らず、日本では考えられないような高貴な名前のオンパレードです。
そんな日本だからでしょうか、大分市の高崎山自然動物園で、生まれたばかりの赤ちゃんザルに付ける名前を公募したところ、「シャーロット」に決まりました。ところがそれに対して、英王室の王女と同じ名前をサルに付けるとは「王室に対して失礼だ」との批判が殺到しました。これに対して、動物園側は、撤回を含めて協議をするとの謝罪文書を発表する騒動にもなりました。当の英王室は「どんな名前を付けようと動物園の自由です」という鷹揚な態度でした。結果として名前の変更はなく、赤ちゃんザルも「シャーロット」と呼ばれることになりました。
高貴な方に対する畏敬の念を示すのは大切なことです。しかし、変にかしこまって遠ざけてしまうより、親しみを込めた対応も必要です。その意味で、赤ちゃんザルにも王女と同じ名前を付けることで、王室に対して近親感を抱きたいとの思いもあったのではないでしょうか。問題は最近の日本人の批判精神です。大局的な見方ではなく、自分たちだけの狭い価値観で、物事を批判しがちです。更には、ネット社会の弊害でしょうか、それを煽るが如く、我も我もと同調する人が出てくることです。それが報道されると尚のこと、世間は騒ぎ立てます。そして「炎上」などと言う思いやりのない言葉で一括りにされてしまします。
生まれたばかりの赤ちゃんは、自分で名前を付けることができません。誰かに命名されるのです。そしてひとつの命が、社会的にデビューすることになるわけです。まさに名前は命です。私たちがいただいた名前は、信念をもって付けて下さったはずです。因みに「寿限無」は『無量寿経』というお経から付けたものだそうです。お経は尊い字のオンパレードです。みなさんの名前の字もお経の中にあるかもしれません。とすれば、名前に恥じない生き方をしたいものです。「炎上」のネタにならないためにも。
それでは又、6月1日よりお耳にかかりましょう。
【第986話】 「道徳の時間」 2015(平成27)年5月11日-20日
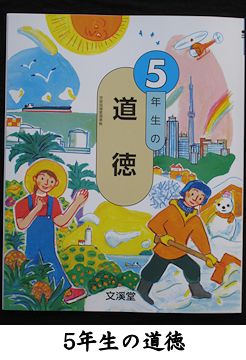 お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第986話です。
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第986話です。
小学校の頃の「道徳の時間」は、実に応用自在でした。時に自由時間、時に体育、時に授業時間が足りなくなった教科の穴埋めにもなったりしました。授業が必要ないほど誰もが道徳的な日常生活を営んでいたのでしょうか。のどかな時代でした。
時は移り、今年度より学習指導要領の一部改正により、教科外活動であった小・中学校の「道徳」を「特別教科 道徳」として、教科へ格上げになりました。その授業用教材の「5年生の道徳」(文渓堂発行)という本に、あの「まけないタオル」が掲載されました。東日本大震災支援として山形の三部住職さんが発案した、50センチと短くて首にも頭にも巻けないけど、震災にも負けないというダジャレを込めたタオルです。苦しくても笑顔になって欲しいという発想から生まれました。被災地に届けるために全国の人に募金を呼びかけました。協力者にもタオルがプレゼントされます。被災者も支援する人も同じタオルでつながって、復興を願うというものです。
この活動を広めるに当たり、歌を作ろうということになりました。私が作詞をし、「歌う尼さん」ことやなせななさんが作曲をして歌っています。全国各地で「まけないタオル」の歌を披露しながら、タオルを届けてきたのです。これまで7万枚を超えるタオルが配られました。タオルのユニークさとやなせさんの歌の力が大きかったのでしょう。
そのやなせさんが、「5年生の道徳」に執筆を依頼され、「まけないタオル」の活動に触れながら、震災で亡くなった多くの人々を悼みつつ、未来ある子どもたちに呼びかけています。それは私がやなせさんに語りかけた言葉の一部でもありました。「震災で亡くなった人は、あの日食べた昼食が生涯で最後の食事となってしまったのです。私たちは三度の食事も、毎日生きていることも当たり前と思ってしまいますが、震災はそうでないことを気づかせてくれました」そんな内容でした。それを踏まえて、やなせさんは「かけがえのない今この時の尊さにはなかなか気づけません。生かされている ''今'' を大切に」と教材の中で結んでいました。
5年生の道徳の学習指導要領を見て、要点を挙げるとすれば、「善悪の判断」「思いやり」「規則の尊重」「生命の尊さ」でしょうか。道徳が教科へ格上げになった理由の一つには、世の中で「生命の軽視」が目立ってきたことが考えられます。元気な子どもに死を実感しろというのは無理かもしれません。しかし、人の命も猫の命も花の命も、それぞれひとつしかないことを実感できる子どもであって欲しいのです。そして時間も命と同じです。今日この日という時間は、ひとつしかありません。今日が過ぎれば、二度と戻ることはできないのです。だからひとつしかない「今という時間」を大切にしたいものです。それは大人にもいえる「道徳の時間」です。
ここでお知らせ致します。4月のカンボジア・エコー募金は、80回×3円で240円でした。ありがとうございました。
それでは又、5月21日よりお耳にかかりましょう。
【第985話】 「善なるもの」 2015(平成27)年5月1日-10日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第985話です。
「エベレストかつては1万5000メートルか」と「チョモランマ総合学術調査隊」が発表しました。今から16年前のこと。エベレストは8,848メートルで世界最高峰。約5千万年前にインドがアジア大陸にぶつかり、広域変成岩が盛り上がり堆積岩の地層を押し上げ、二重構造の山脈になったそうです。2千万年前ごろから、堆積岩が北側へ断層を作りながら、300万年間ゆっくりとずり落ち続けたと考えられていました。その決め手となる断層が発見されたのです。そして堆積岩の厚さは1万メートルになるから、結果エベレストは1万5000メートル以上あったというのです。
エベレストの成り立ちを考えても、ヒマラヤ山脈のおひざ元、ネパールは「地震の巣」で、大地震の発生が懸念されていたといいます。そして4月25日にネパールを中心にマグニチュード7.8の地震が襲いました。エベレストでは雪崩も発生し、日本人を含む登山者も犠牲になっています。死者は5千人を超え、1万人に達する可能性もあります。10年前の2005年にも、ヒマラヤに連なるパキスタン側カシミールの山岳地帯で、マグニチュード7.7の地震が発生し、8万6千人の死者が出ています。
さて、お釈迦さまが生まれたのはネパールで、現在のインドの国境に近いカピラヴァストゥのルンビニという花園です。勿論そのあと、修行をされお悟りを開かれたのはインドの地であり、仏跡の多くはインドに残っています。お釈迦さまが生まれたのは紀元前463年という説があり、今から約2500年前のことです。当時もネパールや北インドは「地震の巣」ではなかったのでしょうか。
仏教学者によれば、お釈迦さまは80年の生涯の中で、地震や津波や火山噴火に遭遇されたという記録はないようだと言います。災害を受けた人々に対する説法は、お経の中には見られないそうです。そしてお釈迦さまは無一物の出家者ですから、被災している人に物質的支援は一切できなかったろうということです。
しかし、お釈迦さまは臨終間際に、最後の弟子スバッタに対して「私は29歳で、何かしら善なるものを求めて出家した」と告げられたそうです。「善なるもの」とは、自分だけにとって善なるものということではありません。他のためにも、今ばかりではなく、未来のためにも「善なるもの」ということでしょう。それは「慈悲」という言葉に置き換えられます。慈悲の慈は喜びを与え、悲は苦しみを除くということです。
ネパールという遠い国に支援に行ける人は限られています。しかし、日々お釈迦さまに手を合わせている私たちは、慈悲の心でネパールに善なるものが訪れるように祈り続けましょう。そして無一物に成りきれていない私たちですから、何がしかの支援の心も届けることができるのではないでしょうか。
それでは又、5月11日よりお耳にかかりましょう。
【第984話】 「1票差」 2015(平成27)年4月21日-30日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第984話です。
4月12日に行われた統一地方選挙前半戦は、知事選も県議選も投票率が過去最低となり、50パーセントに満たないという低迷ぶりです。そんな中で正真正銘の一票の重みを感じる選挙がありました。
相模原市の市会議員選挙では、議員定数18議席で、18番目に当選を果たした得票数は3404票。19番目で落選した得票数は3403票で、しかも2人いました。わずか「1票差」で、2人も落選することとなったのです。因みに、無効票は2487票で、投票用紙の持ち帰りが2票ありました。
2500票余りあった無効票を思えば、落選した人は、あと2票だけでいいから自分に入れて欲しかったと切に思ったことでしょう。投票に来なかった人は更に多いでしょうから、彼らに対して選挙運動期間中に、もうひと押しの訴えが足りなかったと後悔しているかもしれません。わずか1票されど1票です。
一方、熊本市の市会議選挙で定数8議席の南区では、8番目の得票数が4515票で2人同数になりました。そこでくじ引きでの決定となりました。公職選挙法ではくじ引きの方法は示されていないそうです。今回は1-10の数字の棒を順番に引き、小さい数を引いた方を当選とする方式で行われました。予備抽選で引く順を決め、ひとりは「3」をひとりは「10」を引きました。当然「3」を引いた候補者が最後の議席を獲得しました。
どんな選挙でも候補者は、ある程度当選または落選ということを想定していることでしょう。それにしても紹介したふたつの選挙は、千票単位の得票数がなければ当選しません。その中で落選するとすれば、百票単位の差がついてもおかしくないところです。誰が1票差を想定できたでしょう。建て前として「一票の重み」とは言いますが、現実的にそれを実感できることは少ないのではないでしょうか。でも絶対にないことではないのですね。
翻って、私たちの人生は常に1票差だと思っていなければなりません。数える意識もなく呼吸を繰り返していますが、ある時次の一息が出なくなるのです。何票もあると思えば、たった1票の重みが見えてこなくなることがあります。それと同じで、普通に息をしているとき、たった一息の有り難さが分かりません。しかし命の決着はその一息にあるのです。くじ引きもなければ、誰も代わってはくれません。一息を無駄にしない生き方をしていれば、仏さまが最後の議席を用意して下さるでしょう。それは仏さまだけが座ることができる蓮華台です。
それでは又、5月1日よりお耳にかかりましょう。
【第983話】 「3.11という新年度」 2015(平成27)年4月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第983話です。
4月、年度初め。しかし、私の個人的な年度の始まりは3月11日というつもりでいます。勿論、東日本大震災以前には思わなかったことです。
あの日は、もう一つの住職地である徳泉寺の檀家総会が本堂で開かれていました。午後1時30分に開会し、1時間ほどで閉会。総代さんと後片付けをしている時に、2時46分の大地震に襲われました。ただならぬ揺れに、とにかく避難をということで、後片付けもそこそこに寺を離れました。それから1時間もしないうちに大津波に襲われ、本堂も流され、ほとんどの檀家さんの家屋も壊滅状態となりました。あたり一帯は災害危険区域となり、住まいすることができません。
毎年3月11日が来るたびに、震災以前の故郷を思い、震災後の現状に溜息をついてきました。同時にその日をある意味でスタートの日と捉えて、今年こそは少しでも前に進めるようにと、気持ちを奮い立たせてもきました。
今年も震災の日と檀家総会の日が巡ってきました。檀家総会は都合により、3月末日に行われました。檀家さんも少しずつ落ち着くところが定まりつつあります。例年よりは明るい雰囲気で議事が進行しました。最後の議題として、本堂の再建について提案しました。この4年間で一番の迷いは現地再建ができるかどうかでした。人が住まいできないものの、建物を建てることは可能です。しかし、そういうところに、お寺が存在しても意義があるのだろうかという疑問です。新天地への移転も考えましたが、現実問題としては、然るべき土地を確保することは、夢のような話です。
現地に再建して、復興のシンボルとしてお寺があれば、住まいがなくなった人も、故郷を訪ねやすいのではないかと考えました。そこに集う人々が多目的に利用できる場所となれば、生きたお寺としての意義があります。何より本堂は流されたものの、本尊さまは奇跡的に発見され、新たに「一心本尊」と名付けられ広く紹介されました。早く復興して下さいという願いを込めた「はがき一文字写経」の納経志納が、全国から寄せられて、4500口を超えています。難を逃れた本尊さんの功徳が、みなさんの心の拠りどころとなり、故郷の災難を鎮めてくれると信じれば、現地再建しかありません。
檀家さんもこの日を待っていたとばかりに、全員賛同して下さり、復興に向けて具体的な図面が描かれ、震災5年目の新年度が始まりました。「逃げない はればれと立ち向かう それが僕のモットーだ」岡本太郎の言葉です。津波が来たら逃げますが、一心本尊さまと共に、故郷の明日に立ち向かいましょう。
ここでお知らせ致します。3月のカンボジア・エコー募金は、82回×3円で246円でした。ありがとうございました。
それでは又、4月21日よりお耳にかかりましょう。
【第982話】 「平成の少年」 2015(平成27)年4月1日-10日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第982話です。
年号が平成に替わる直前の昭和64年1月4日のこと、当時17歳の女子高生が40日間も監禁された上、火をつけるなどの暴行を受け死亡。遺体はドラム缶にコンクリート詰めされ捨てられるという事件が東京都足立区綾瀬でありました。犯人は18歳から16歳の少年4人でした。検察側は「人の仮面をかぶった鬼畜の所業」とまで断じました。しかし、犯人たちを幼児から知る地元の大人は「普通の子」だったと言っていました。
この事件は暗い平成の幕開けだったのでしょうか。その後も少年による残虐な犯罪は絶えません。ここ数年殺人容疑で逮捕された未成年者は年間50人前後にのぼっているそうです。今年2月、川崎市の多摩川河川敷で、中学1年の上村遼太(うえむらりょうた)さん(13歳)が遺体で発見されました。犯人は18歳と17歳の少年3人です。2月20日午前2時ごろ、主犯格の18歳の少年は、上村さんを裸にして川に入れ、泳がせました。川から上がるとカッターナイフで切りつけるなどの暴行を加えました。17歳の少年は18歳の少年に脅され、上村さんに謝りながら切りつけたことを認めています。
どんな理由があるにせよ、人の命を殺めていいはずがありません。いじめの傾向を見ていると、強い者に対する反抗ができなくて、いきおい弱い者にその矛先が向かっているようです。そしてすぐに激怒して、キレてしまいます。子どもたちの想像力や抑止力が育ちにくい平成という時代なのでしょうか。そんな時代に今一度お釈迦さまの言葉をかみしめて下さい。
お釈迦さまは今から2500年前の4月8日に、ヒマラヤ山脈の麓の釈迦族の王子としてお生まれになりました。生まれてすぐに、東西南北に7歩歩かれ、右手で天を、左手で地を差して、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と言われました。この世界で自分より尊いものはないという意味です。「唯我独尊」を勘違いされては困りますが、自分だけが大事だから、自分の好き勝手にふるまっていいということではありません。それではまさに、想像力も抑止力もない少年と同じです。
「自分が尊い」と私が思っているように、自分以外の人もそう思っているという想像力を働かせて下さい。即ちすべての存在と命がこの上なく尊いということです。お互いにたったひとつしかない命をどうして粗末にできるのですか。
少年たちも確かに「普通の子」だったでしょう。姿かたちは違っても、みんなひとつの命をいただき、縁あって同じ時代に生きているのです。この奇跡のような存在を、有ることが難しいのに今こうして有るので「有り難い」というのです。普通に想像できれば、感謝こそすれ、すぐキレるような癇癪はなくなります。
それでは又、4月11日よりお耳にかかりましょう。
【第981話】 「復興へわたる」 2015(平成27)年3月21日-31日
お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第981話です。
尺取り虫はその進むさまが、親指と人差し指を使って「5寸・1尺」と長さを計るのに似ているので、そう名付けられたそうです。そして「尺度」の「度」は、尺取り虫のように、手尺で一つ二つとわたって長さを計る意味があります。転じて「わたす」とも読みますが、仏の教えによって彼岸にわたすなどと言うときに使います。
彼岸とは彼の岸、仏さまの世界を言いますが、理想の世界と言ってもいいでしょう。それに対してこちらの岸もあるわけで、それを此岸といいます。仏さまに対して、凡夫の世界、私たちが今いる現実の世界と言えます。悩み苦しみ多い現実から、いつも清々しい心持でいられる理想の世界にわたられるようにと発心することが、お彼岸の第一歩とも言えます。
さて、現在徳本寺の境内には、東日本大震災復興祈願法要に合わせて掲げられた、たくさんの「黄色いハンカチ」が風になびいています。震災以降、山元町には国内外から復興を支援する「黄色いハンカチ」が、2万1000枚も寄せられています。被災者を励ます様々なメッセージが書かれています。大人から子どもまで、人柄が伝わるような文字や絵が踊っています。ロープに等間隔で結びつけられた何枚ものハンカチを見ていると、彼岸の教えと重なってきました。
「黄色いハンカチ」は、何かの橋渡しの役割も担っているのではという思いにさせられます。「度(わた)す」とは、一つ二つとわたって長さを計ることからきていると言いました。黄色いハンカチも一枚二枚と、わたっていけます。被災地というたいへんな現実から、復興という理想の世界へ、被災者をわたしてくれる力があるような気がします。
復興祈願法要では、「山元町の歌を作り隊」というバンドのコンサートもありました。彼らは先に、震災後も悲しみを乗り越えて山元町で生きていくという内容の歌「この町で」を発表して、多くの共感を集めています。そしてこの度、黄色いハンカチのイメージソングとして「黄色いハンカチ」という歌も披露してくれました。ハンカチを届けてくれた方への感謝と震災から4年が過ぎ少し前向きになってきた想いを込めています。
'' なくした夢 あきらめた想い ひとつひとつ拾い集めて いつか叶うまで 信じ続けていこう メッセージからの勇気 ''と歌っています。一枚一枚の黄色いハンカチが、被災という現実から、復興という理想へわたって下さいと願っています。私たちは、なくした夢やあきらめた想いを、ひとつひとつ拾い集めて、叶うと信じることが、彼岸へわたる第一歩になるのではないでしょうか。復興の尺度は人それぞれでしょうが、尺取り虫に負けない確かな足取りで進みましょう。
それでは又、4月1日よりお耳にかかりましょう。
【第980話】 「般若の風」 2015(平成27)年3月11日-20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第980話です。
「般若心経」は262文字で、比較的短いお経といえます。一方般若心経の原典ともいえる「大般若経」は、約480万文字で600巻もあります。一字一句読むのは至難なことです。そこで「転読」と言って、お経本を扇のように広げて読む作法が、古来より行われてきました。
東日本大震災から丸4年が経とうとしている3月8日、徳本寺本堂で復興祈願法要と大震災で亡くなられた方の慰霊法要が行われました。10人を超える亘理郡内の和尚さんにより、勢いよく大般若経の転読がなされました。お経を読む代わりに呪文を唱えながら転読します。「諸法皆是因縁生(しょほうかいぜいんねんしょう) 因縁生故無自性(いんねんしょうこむじしょう) 云々」と唱えて、1巻ずつ転読されていきます。一斉に扇のように経本が広げられる様は見事であり、そこに「般若の風」も感じます。
大般若経は中国の玄奘三蔵法師が、今から1400年ほど前に16年の歳月をかけてインドから持ち帰ったものです。更に4年かけて梵語から漢訳され、今に伝わる「大般若経」になっています。様々な困難や危険を乗り越えてインドから伝えられたこのお経の文字通りの「有り難さ」は、誰もが感じたことでしょう。日本でも災害消滅や病気平癒などを祈願するときに、大般若経が転読されてきました。
そのお経には仏教の根本思想ともいえる「空」の教えが説かれています。呪文にあるように、「諸法は皆是因縁より生ず 因縁生の故に自性なし」即ち、一切の存在・現象は皆、因縁によって生じたものであり、固有の本体はないので、絶えず変化して止まない、それを「空」といいます。「空」とは固有の本体がないということでは「空っぽ」ですが、縁によって成り立っている存在・現象は仮の姿だから、常に変化していくとも捉えなければなりません。つまり無常ということでもあります。
大震災もひとつの縁といえます。それによって生じたこの被災状況。これも仮の姿なれば、変化し続けることができます。事実被災地の風景は、変わってきました。ただ個々人の心の風景には、まだもやもやとしたものがあるかもしれません。そんな人にも、この度の般若の風が吹いて、少しは心のもやが晴れてくれたらと願い、法要を勤めました。それが復興につながれば、般若の功徳です。
復興に向かうとは、どんなに空であっても、過去の時間に戻ることはできないのだから、いかに未来の時間を描こうかと覚悟を決めることではないでしょうか。「過去はコントロールできない。未来のコントロールをめざすことが大事でしょう」。元大リーガーの松井秀喜の言葉です。般若の風を追い風にして、未来への決め球をズバリ投げ込みましょう。
ここでお知らせ致します。2月のカンボジア・エコー募金は、76回×3円で228円でした。ありがとうございました。
それでは又、3月21日よりお耳にかかりましょう。
【第979話】 「貸出しカード」 2015(平成27)年3月1日-10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第979話です。
―「あったよねこの本うちに」流された家の子が言ふ移動図書館―今年の歌会始に選ばれた千葉県の平井敬子さんの歌です。この移動図書館とは、もしかしたらシャンティ国際ボランティア会が東日本大震災被災地で行っている移動図書館活動のことかもしれません。わが故郷宮城県山元町にも、震災翌年の平成24年9月より、シャンティによる移動図書館活動が行われています。
山元町は沿岸部に位置し、可住地域の60%が浸水しました。浸水割合は県内最大クラス。家屋の40%にあたる2,217棟が全壊し、その内の約半数は流出です。当時の震災瓦礫は53万3千トンで、町のゴミの量に換算すると、実に152年分に相当するそうです。それまで当たり前に身の回りにあった、ありとあらゆるものが流されてしまったのです、愛読書も含めて。635人もの尊い命も犠牲となってしまい、人々の喪失感は想像を絶するものがあります。
被災した人々は緊急避難所生活を経て、仮設住宅に住まいするようになったものの、衣食住が十分に足りているとは言えません。それでも人はパンのみにて生きるに非ずです。心の栄養補給もなくてはなりません。そんな時にシャンティの移動図書館活動という支援がやって来たのです。
仮設住宅に玄関横づけともいえる親しみやすい移動図書館車は人々に歓迎され、8カ所の仮設住宅を月2回くらいの割合で運行します。1カ所あたり1時間ほどの「開館」ですが、「立ち読み お茶のみ おたのしみ」というキャッチフレーズの如き活動が展開されます。たとえ借りる本がなくても、誰かに会えてお茶の接待を受けられることを心待ちにしているようです。
それでも利用者数と貸出本の冊数は年々減少しています。運行初年度は3カ月間だけでしたので、759人の利用者で、1,382冊の貸出しでした。翌年平成25年は2,568人で6,310冊、平成26年は2,083人で4,269冊でした。1年間で500人と2,000冊減っていることになります。その主な原因は明らかです。仮設住宅を出ていく人が増えているということです。それは喜ばしいことなのです。何もかも流されて仮の住まいから、普通の日用品に囲まれた定住地に落ち着けることが、復興の最小限度の到達点でしょう。
移動図書館をよく利用して、現在は新たな定住地に移った方が言っていました。移動図書館で使った貸出カードは、仮設住宅の暮らしを象徴する思い出の品となり、捨てられずに大切にしまっているそうです。本を含めた思い出の数々が流され、憔悴し切っていたとき、移動図書館で心の栄養補給ができた人も確かにいたのです。そして、今度は一枚の貸出しカードという思い出ができ、それを肥やしに、新天地で新しい芽を育む人が、一人でも多く生まれる震災5年目でありますように願うものです。
それでは又、3月11日よりお耳にかかりましょう。
